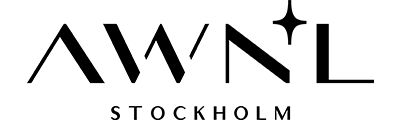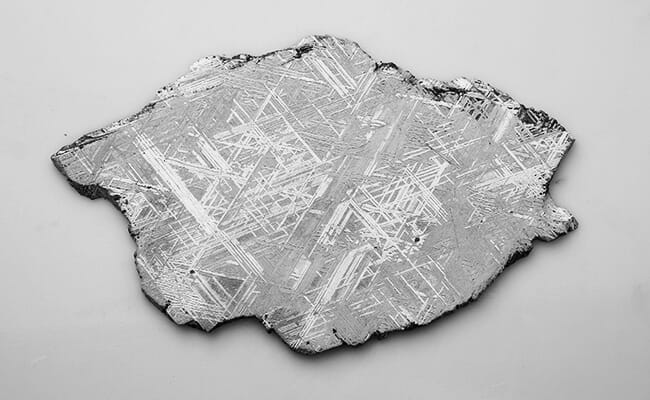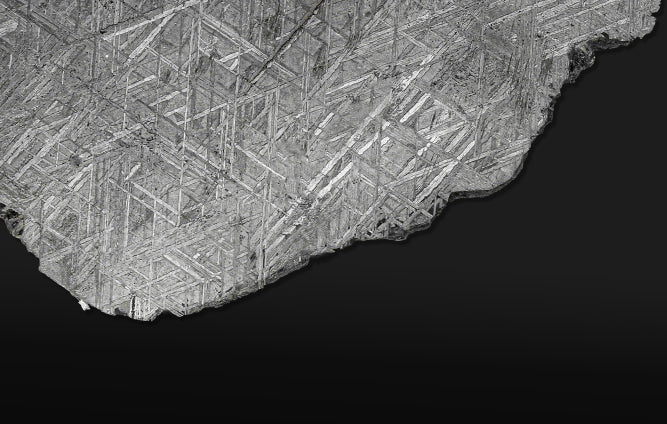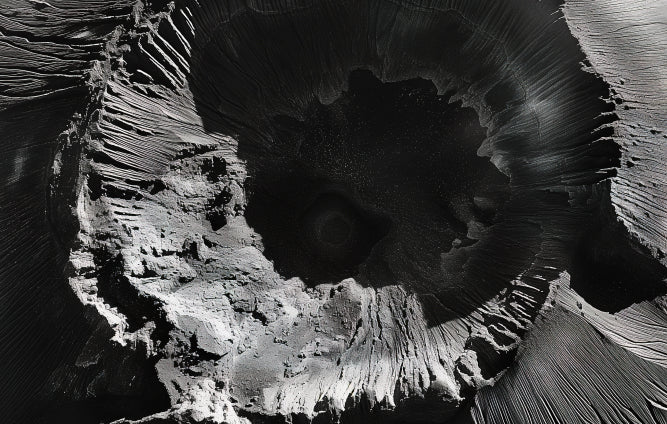「悪魔の目」とは何か?世界に伝わる「目」のシンボルの真実
「悪魔の目」。その言葉を聞くと、どこか不吉で恐ろしいイメージが浮かぶ方も多いでしょう。しかし、実はこの「目」は、古代から多くの文化で「人を守るシンボル」として大切にされてきました。怖いどころか、私たちを守る「盾」のような存在なのです。
今回は、この「悪魔の目」の意味や歴史、現代でも人気の理由についてご紹介します。
「悪魔の目」の起源と意味
中東雑貨やトルコ旅行が好きな方なら、一度は目にしたことがあるはずの「青い目」。「悪魔の目」は、英語で Devil's Eye(デビルズ・アイ)や Evil Eye(イービルアイ)と呼ばれます。そのルーツは古代ギリシャ、中東、北アフリカなどに広がっており、「邪視(じゃし)」=他人の悪意ある視線から身を守るお守りとして知られてきました。
目の形のモチーフ
このシンボルは「目」の形をした装飾品や護符として使われることが多く、特に有名なのはトルコ発祥のナザール・ボンジュウ(Nazar Boncuğu)という青と白の目のチャーム。壁や玄関、車内、アクセサリーなどに飾ると、嫉妬や災いから身を守ってくれると言われています。
トルコ人は、嫉妬や悪意をもった「邪視」が災いや病気を招くと信じてきました。特に、美しい女性や子ども、社会的に成功している人ほど、他人からの嫉妬を受けやすいと考えられていたのです。
そのため、トルコでは赤ちゃんが生まれた際に、この「青い目」を身につけさせる習慣があります。子どもがすくすく無事に育つよう、悪意から守るお守りとして広く使われているのです。

トルコのお守り、ナザール・ボンジュウ, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
色の意味
ナザール・ボンジュウは、多くの場合「青と白」の同心円で描かれた目の形をしています。青色は「浄化」「保護」の象徴で、ガラス細工として一つひとつ手作りされることが一般的。
中には「青と黄」のデザインもあり、デザインはさまざまですが、どれも「邪気を吸い取り、守ってくれる目」として親しまれています。
もし、このお守りが割れたら、それは「災厄を一つ防いだ証」。割れた瞬間に新しいナザールを用意するのが伝統です。
文化によって異なる「悪魔の目」の役割
「悪魔の目」は、実は文化によって少しずつ役割が異なります。
-
中東・トルコ
ナザール・ボンジュウが最も有名。青色は「幸運」と「浄化」の色。赤ちゃんや新築の家に贈る風習もあり、愛されるお守りです。
-
ギリシャ
「マティ」とも呼ばれ、古代から海運の守護や旅の安全を祈るシンボルとしても利用されてきました。
-
イタリア
「マロッキオ」という概念で知られ、魔除けとして角や手のシンボルと併用されることも。
つまり、国や地域によって微妙に意味が変化しつつも、共通して「邪悪なものから身を守る力」として信じられてきたのです。
複数ある「青い目」の伝承
ナザール・ボンジュウには、いくつかの面白い言い伝えがあります。
■異民族の青い目の伝説
かつて、青い目を持つ異民族が周辺部族を恐怖に陥れたことがありました。人々は「青い目」が不吉の象徴と考え、「邪には邪を」という発想から、青い目を模したお守りを飾ったと言われています。
■ギリシャ神話・メデューサの説
別の説では、ギリシャ神話のメデューサの目がルーツとも。美しさゆえに呪われ、目を合わせた者を石に変えてしまうメデューサの目が、悪意を見抜き、はね返す力として信仰されたという話も残っています。
■古代メソポタミアの葬送儀式
さらに古代メソポタミア文明では、死者の首に「青い目」をかける葬送儀式があったことも判明しています。来世での幸運や保護を祈るための儀式だったと言われ、多くの遺跡でも青い目のモチーフが発見されています。
現代における「悪魔の目」
SNSやファッションでも、最近は「悪魔の目」をモチーフにしたアイテムをよく目にします。ネックレスやブレスレット、キーチャームなど、現代人にとっては「おしゃれなお守り」として人気です。
さらに、目のモチーフは心理的にも「見守られている安心感」や「冷静な視点」を与えてくれると言われ、日常の中で無意識に心を落ち着かせる効果も期待されています。
まとめ
「悪魔の目」は、恐ろしいものではなく、「悪意を見つけてはじき返す」古代から続く知恵そのもの。あなたももし最近「ツイてないな…」と感じることがあれば、このシンボルを取り入れてみてはいかがでしょうか。世界中で長く愛されてきた理由が、きっと少しわかるはずです。